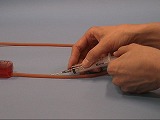看護学習教材
従来の看護技術教育の理論と実習を統合し、グループで探究的、行動的に学習する方式に変えて、一人ひとりが速く、確実に技術をマスターできるよう工夫した学習教材です。
個別の学習内容および教材については、それぞれのページをご参照ください。
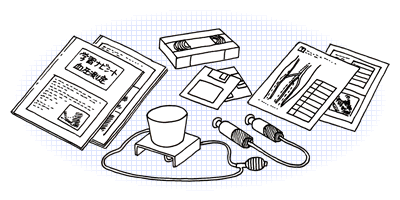
■
血圧測定の学習
■
採血の学習
■
ベッドメーキングの学習
■
仲間とみがく看護のコミュニケーション
1.血圧計のしくみを調べる
|
学習順序の例
[通常の場合]
1→2→3→4→5→6
[別パターン]
3→1→2→4→5→6
※こちらの図式をご参照ください
→PDFファイル
|
2.血圧計の操作練習
- 送気球の片手操作練習
- 目盛りの読み取り練習
- マンシェットの巻き方
|
3.血液循環のしくみと血圧
- 心臓の収縮拡張で血液を循環させるしくみ
- 血流は脈流、血圧は脈圧
- 最高血圧と最低血圧
|
4.血圧を測る
- コロトコフ音とはどういう音か
- 測定位置(上腕動脈の末端)を探す
- 最高血圧、最低血圧の読み取り方
|
5.血圧測定の原理
- 外圧が流れの断続を生み出す
- 流れの断続が音を発生させる
- 外圧の測定で内圧(血圧)が測れるわけ
|
6.測定の条件と血圧値の関係
|
 原理は血流をシミュレーションできる構案教材
原理は血流をシミュレーションできる構案教材
(血圧測定原理学習用シミュレータ*) を使って研究
*血圧測定原理学習用シミュレータ
JADECが開発して特許を取得、株式会社坂本モデルが「けつあつくん」として商品化し販売中です。≫
ページを見る
| 学習の段階 |
学習の内容 |
学習活動 |
第1ステップ
要素行動のポイントとその練習 |
- 学習目標をつかむ
|
|
- 針の選択と注射器への接続
|
- 各種サイズの注射器、針の観察
- 血管モデルと針の太さとの比較
- 注射器の構造を調べる
|
- 部位の選択と駆血
*血管の走行と採血部位
*駆血帯の締め方
*血管の固定 |
- 血管走行図を参考に、自分友人の血管の走行を調べ、採血部位をさがす
- モデル行動を観察し、駆血のしかた、血管の固定のしかたを調べる
[駆血の練習]
|
- 血液の吸引
*針の固定
*吸引時の注射器の操作
*針の引き抜き方 |
- モデル行動の観察(映像)
- シミュレータを対象に、注射器の持ち方、吸引のしかたを研究する
[吸引の練習](下の写真参照)
|
第2ステップ
合理的な行動の設計と実施 |
- 合理的な行動の場を設計する
|
|
- 連続行動としてのプロセスを設計する
|
- 学習したことを総合し、合理的な手順を考え、実施する
- モデル行動(VTR)と比較検討、修正する
|
(注)今回は、時間の都合で第1ステップのみ学習した。
|
最初はゴム管で、針を刺す角度、深さなどを研究
|
|
最後は血管シミュレータで総合的に練習
|
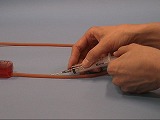
|
|

|
*採血の学習用シミュレータ
JADECのアイデアを基に、株式会社坂本モデルが静脈注射のシミュレータ「けっかんくん」として商品化して販売中です。≫
ページを見るベッドメーキングの学習
| 学習の段階 | 学習項目 | 学習活動 |
|---|
第1ステップ
要素行動のポイントとその練習 | - 学習目標をつかむ
| |
|---|
- 出来上がりのベッドを調べる
| - 出来上がりのベッドをはがして調べる
- 出来上がりのベッドに寝てみて調べる
敷いてあるものとその順番、角の作り方端の位置、折り返し方、それらの理由
|
- 角をつくる(三角,四角)
| - 折り紙で三角,四角をつくる
- シーツでの三角、四角のつくりかた
- モデルの行動の観察(映像)
姿勢とその変化、手の使い方
[練習] シーツを敷く、毛布を敷く
|
- 広げる、たたむ
| - ベッドとシーツ、毛布の大きさの関係を調べる
- たたみ方を調べ、置き方広げ方を考える
[練習]シーツ、毛布を広げる、たたむ
|
第2ステップ
合理的な行動の設計と実施 | - 合理的な行動の場を設計する
| |
|---|
- 連続行動としてのプロセスを設計する
| - 学習したことを総合し、合理的な手順を考え、実施する
- モデル行動(映像)と比較検討、修正する
|
仲間とみがく看護のコミュニケーション
対象に即座に対応する反応力を高めるよう工夫した新しいスタイルのテキストブックです。
大森武子氏(東京女子医科大看護短大教授(当時):現名誉教授)、大下静香氏(福島県立医科大看護学部教授(当時))と共同執筆しました。
株式会社医歯薬出版から出版されています。(2003年) ≫
ページを見る
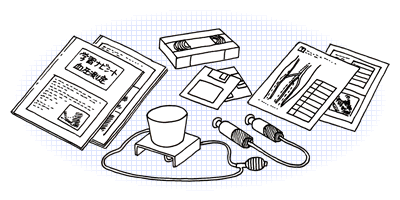
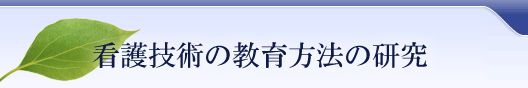
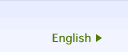
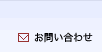
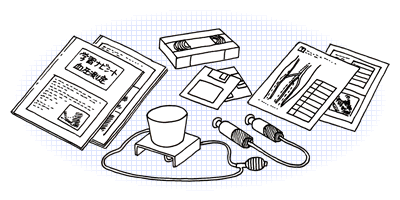

 原理は血流をシミュレーションできる構案教材
原理は血流をシミュレーションできる構案教材